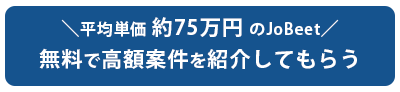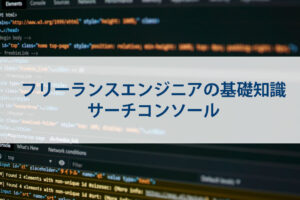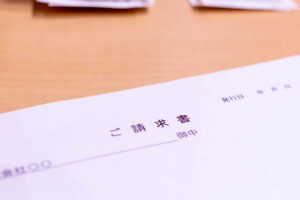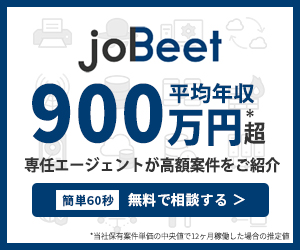フリーランスエンジニアの方とお話をしていると、ときとき会社設立(法人成り)の話題になることがあります。フリーランスエンジニアとしての活動が起動に乗って、収入が増えてくると個人事業主として税金を納めるよりも、会社を設立(法人成り)して税金を納めたほうが節税に期待できるのは事実です。とはいえ、会社を設立(法人成り)することで個人事業主時代とは異なるデメリットも発生します。今回は、フリーランスエンジニアの「会社設立(法人成り)」について詳しく見ていきたいと思います。
もくじ
会社設立(法人成り)で節税効果が期待できる理由とは?
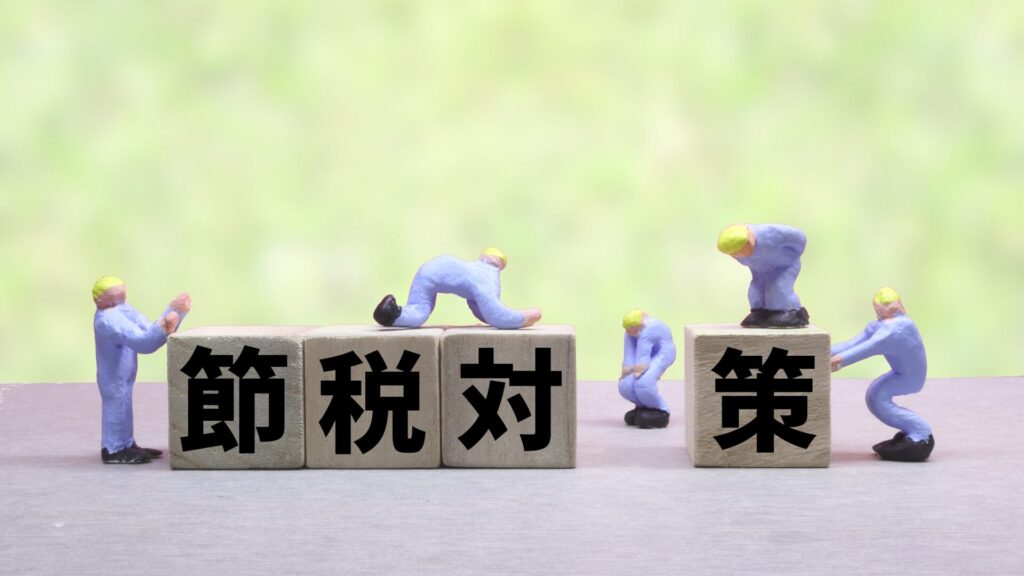
2021年10月現在、日本における個人の所得税率は5%~45%となっています。フリーランスエンジニア(個人事業主)として活動を行っている場合、売上から経費を引いた収入(事業所得)はすべて個人所得として扱われるため、前述の所得税率に基づき税金を納める必要があります。
一方で、法人(会社)として活動を行った場合の税率は800万円以内の利益部分は15.0%、800万円超の利益部分は23.2%となります。また月々の収入を役員報酬として受け取ることで課税対象となる収入を減らすこともできるため、フリーランスエンジニアとしての収入次第では会社を設立(法人成り)をして税金を納めたほうが節税になることがあります。
次からは、実際の収入を例に挙げながら期待できる節税効果や、会社設立(法人成り)を検討すべき収入額について見ていこうと思います。
会社設立(法人成り)を考える目安の収入と節税効果は?
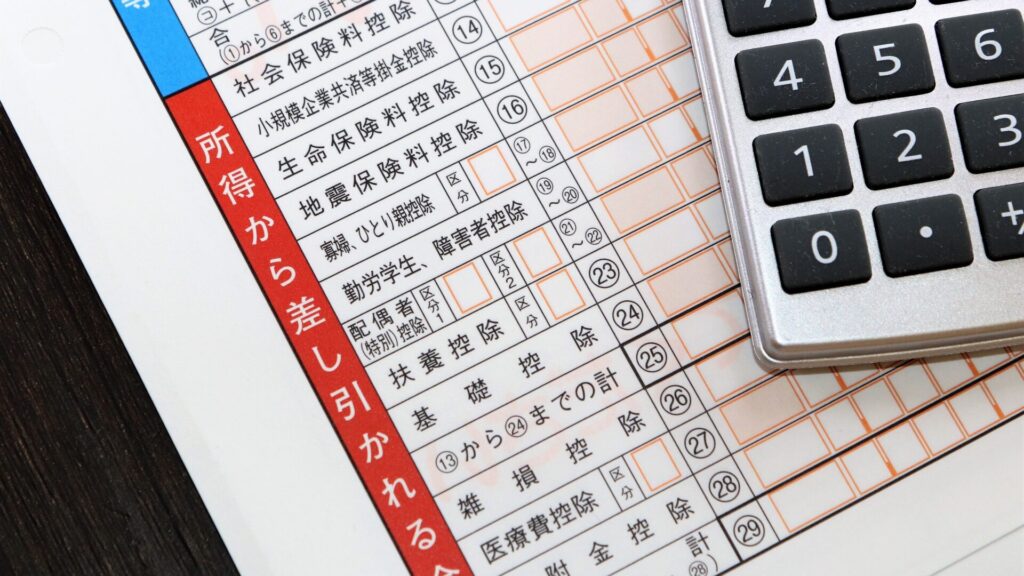
一般的にフリーランスエンジニア(個人事業主)の方が会社設立(法人成り)を考える目安の収入は、年間500万円前後と言われています。なおここであげている収入は、年間の売上ではなく「売上から経費を引いた利益」を指していますので注意してください。
それでは具体的な年間収入を例に使いながら、フリーランスエンジニアとして税金を納める場合と、会社を設立(法人成り)して税金を納める場合にどれくらいの差がでるのかをチェックしていましょう。なお、今回の例は前提条件として下記を設定しています。前提条件が変わると税額も変化しますので注意してください。
<前提条件>
- 個人の住民税は考慮しない
- 個人事業税の税率は5%
- 個人事業主として青色申告を行い、特別控除65万円の適用条件を満たしている
- 会社設立(法人成り)後、自分の役員報酬はフリーランス時代の収入(利益)と同額とする
年間の収入(利益)300万円の場合
結論:フリーランスエンジニア(個人事業主)のほうが年間76,000円節税できます
・フリーランスエンジニア(個人事業主)の場合
①所得税額
計算式 :(年間収入 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 ) * 所得税率 – 控除額
実際の計算:(300万円 – 65万円 – 48万円 ) * 5% – 0万円 = 9.35万円
②個人事業主税額
計算式 :(年間収入 – 290万円 ) * 個人事業主税率
実際の計算:(300万円 – 290万円 ) * 5% = 0.5万円
③所得税額+個人事業主税の総額(①+②)
計算式 : 所得税額 + 個人事業主税額
実際の計算: 9.35万円 + 0.5万円 = 9.85万円
・会社を設立(法人成り)した場合
①所得税額
計算式 :(年間収入 – 給与所得控除 ) * 所得税率 – 控除額
実際の計算:(300万円 – 98万円 ) * 5% – 9.75万円 = 10.45万円
②法人住民税の均等割額
計算式 : 7万円
実際の計算: 7万円
③所得税+法人住民税の均等割額(①+②)
計算式 : 所得税額 + 法人住民税の均等割額
実際の計算: 10.45万円 + 7万円 = 17.45万円
年間の収入(利益)500万円の場合
結論:会社を設立(法人成り)したほうが年間97,000円節税できます
・フリーランスエンジニア(個人事業主)の場合
①所得税額
計算式 :(年間収入 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 ) * 所得税率 – 控除額
実際の計算:(500万円 – 65万円 – 48万円 ) * 20% – 42.75万円 = 34.65万円
②個人事業主税額
計算式 :(年間収入 – 290万円 ) * 個人事業主税率
実際の計算:(500万円 – 290万円 ) * 5% = 10.5万円
③所得税額+個人事業主税の総額(①+②)
計算式 : 所得税額 + 個人事業主税額
実際の計算: 34.65万円 + 10.5万円 = 45.15万円
・会社を設立(法人成り)した場合
①所得税額
計算式 :(年間収入 – 給与所得控除 ) * 所得税率 – 控除額
実際の計算:(500万円 – 144万円 ) * 20% – 42.75万円 = 28.45万円
②法人住民税の均等割額
計算式 : 7万円
実際の計算: 7万円
③所得税+法人住民税の均等割額(①+②)
計算式 : 所得税額 + 法人住民税の均等割額
実際の計算: 28.45万円 + 7万円 = 35.45万円
年間の収入(利益)1,000万円の場合
結論:会社を設立(法人成り)したほうが年間473,600円節税できます
・フリーランスエンジニア(個人事業主)の場合
①所得税額
計算式 :(年間収入 – 青色申告特別控除 – 基礎控除 ) * 所得税率 – 控除額
実際の計算:(1,000万円 – 65万円 – 48万円 ) * 23% – 42.75万円 = 140.41万円
②個人事業主税額
計算式 :(年間収入 – 290万円 ) * 個人事業主税率
実際の計算:(1,000万円 – 290万円 ) * 5% = 35.5万円
③所得税額+個人事業主税の総額(①+②)
計算式 : 所得税額 + 個人事業主税額
実際の計算: 140.41万円 + 35.5万円 = 175.91万円
・会社を設立(法人成り)した場合
①所得税額
計算式 :(年間収入 – 給与所得控除 ) * 所得税率 – 控除額
実際の計算:(1,000万円 – 195万円 ) * 20% – 63.6万円 = 121.55万円
②法人住民税の均等割額
計算式 : 7万円
実際の計算: 7万円
③所得税+法人住民税の均等割額(①+②)
計算式 : 所得税額 + 法人住民税の均等割額
実際の計算: 121.55万円 + 7万円 = 128.55万円
これらの計算式で使用されている所得税の税率や、給与所得控除額の計算方法に関して詳細をお知りになりたい方は、国税庁のWebサイトをご参照ください。
またこれから青色申告に向けて準備を行われたいという方は、下記の記事をご参照ください。
会社設立(法人成り)して役員報酬で収入を得る場合の注意点

年間の収入が上がればあがるほど、フリーランスエンジニア(個人事業主)として活動を続けるより、会社を設立(法人成り)して役員報酬として収入を得た方が節税効果があることがわかりました。冒頭でご説明した法人税は、企業が1年の活動を通じて得た最終的な利益に対して発生するものです。そのため、毎月の利益を全額役員報酬として受け取れば法人税は一切納めなくてよくなるのではないかと考えた方もいらっしゃるのでしょうか?
このような考えを防止するために、役員報酬には下記のような制限が設けられています。
- 役員報酬は1年間、毎月同じ金額であること
- 利益に応じて支払われる業績連動給与は、オーナー経営者には使えない
- 役員報酬の変更は事業年度開始から3ヶ月以内のみ行える
この制限を平たく言うと、フリーランスエンジニアが会社を設立(法人成り)して、3ヶ月以内に年度末までの役員報酬を自分で決める必要がある、ということになります。役員報酬を少し高めに設定しておき、会社の利益が自分の役員報酬に達しなかった場合は、受け取った報酬の一部を会社に貸し付ける(役員借入金と呼びます)ことで利益を調整している方も少数いらっしゃるようですが、会社から見れば役員とはいえ第三者に借りていることに変わりありません。将来的に事業を拡大しようとして銀行に資金を融資してもらう際に債務超過と捉えられて融資を断られたり原因になりがちです。またあなたが亡くなって家族に遺産を相続する際には相続税の対象になるなどデメリットが多数ありますので、役員報酬の設定はくれぐれも慎重に行うことをおすすめします。
会社設立(法人成り)のメリット

会社を設立(法人成り)ことで、所得税の面で節税効果が得られることがわかりましたが、この他にも会社を設立するメリットがいくつかありますのでご紹介していきます。
決算月を自由に決められる
フリーランスエンジニアとして活動している場合、事業年度は1月~12月までと決まっていますが、法人化することで決済時期を自由に決めることが可能です。これにより、繁忙期は仕事に集中、案件数が減る時期に決算作業を行うことができるようになります。
社会的な信頼がアップする
働き方の多様化が進んだことにより、フリーランスエンジニアの社会的信頼度もアップしていますが、会社を設立することで更に社会的な信頼の向上が期待できます。また一部の企業では個人事業主との取引を行わないところもあるため、新しい顧客を獲得するチャンスが広がる可能性もあるといえるでしょう。
設立から2年間は消費税を納めなくてもよい
会社設立(法人成り)から2年間は、年間の課税売上高が1,000万円を超えても消費税の納税義務が免除されます。フリーランスエンジニアとして開業した後も2年間は、消費税の納税義務はありませんので、開業から2年の間に年間の収益が1,000万円を超える場合などは会社を設立(法人成り)することで消費税の納税義務機関を2年間延長することが可能です。なお、2023年10月から開始される「インボイス制度」により消費税の取り扱いが変更になります。詳しくは「フリーランスエンジニアなら必ず知っておきたいインボイス制度をわかりやすく解説。」をご覧ください。
会社設立(法人成り)のデメリット
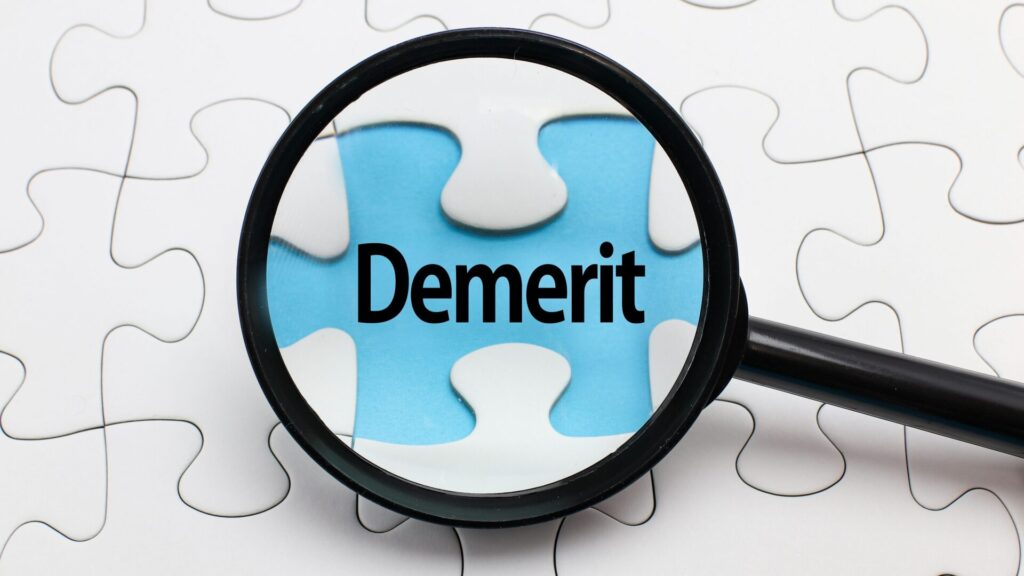
続いて会社設立(法人成り)によるデメリットについてご説明します。金銭面に関わることはもちろん、本業以外の雑務に関わることもありますのでしっかりと確認ください。
費用がかかる
会社設立(法人成り)時には、最低でも30万円程度の費用が必要になります。
※株式会社設立時
フリーランスエンジニア(個人事業主)の時よりも会計が複雑になる
法人の経理処理はフリーランスエンジニア(個人事業主)に比べて煩雑なことが多く、必要な場合は税理士などに会計を依頼しなくてはならない場合もあります。最近はクラウド型の会計ソフトが安価で利用できますので、下記のようなサービスを利用するのも手です。
おすすめのクラウド型会計ソフト
社会保険への加入義務が発生する
あなた1人の会社であっても、フリーランスエンジニア(個人事業主)時代に加入していた国民健康保険と国民年金ではなく、保険料が高額な社会保険(健康保険と厚生年金保険)への加入が必須になります。
法人住民税の均等割がかかる
会社が赤字でも法人住民税の均等割は毎年発生します。
まとめ
今回はフリーランスエンジニア(個人事業主)の方が会社を設立(法人成り)することで得られるメリットやデメリットについて見てきました。節税効果が得られることもはもちろん、社会的な信頼度をアップさせるためにも有効な会社設立(法人成り)ですが、実際に踏み切る際はその効果を最大化するできよう、事業の利益状況やタイミングを十分考慮した上で行うのが大切です。会社設立(法人成り)はゴールではなく、あなたの事業を成功に導くための手段の一つにすぎません。設立後は会社がどのような状態になっていることを目指すのかなどのイメージを十分に描き、詳細に計画を立ててから臨まれることを強くおすすめします。